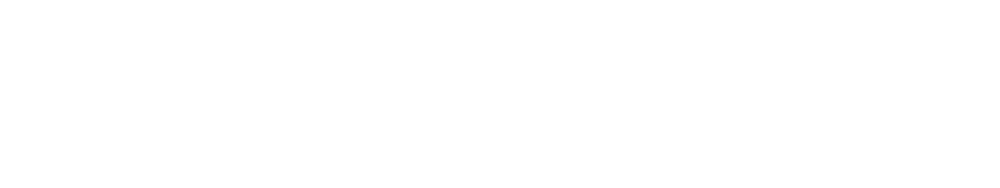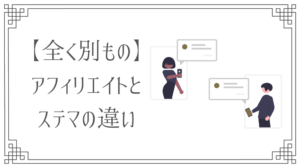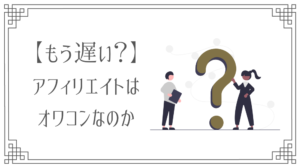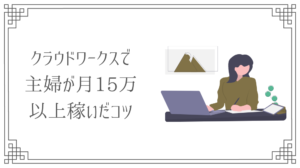「情報商材」と聞くと、みなさんどんなイメージを抱きますか?
 .
.情報商材ってなんか怪しい・・・
詐欺っぽい
と思う人が多いのではないでしょうか?



確かに、情報商材の中には詐欺のような商材もあります。それは事実です。
しかし、情報商材のすべてがイメージしているような怪しい商材というわけではありません。
今回の記事では、
- 情報商材って全部詐欺じゃないの?買っても大丈夫?
- 今買おうと思っている商材が詐欺じゃないか不安・・・
という方に向けて、情報商材が怪しくない理由や、詐欺情報商材の見分け方について解説していきます!
情報商材は怪しい?【結論:怪しくありません】
結論から言うと、
あなたが聞いたことがある、もしかしたら使ったことがあるサービスの中にも、情報商材が含まれているかもしれません。
例えば、
- 進研ゼミ
- ユーキャン
- スピードラーニング
なんかも、情報商材です。
情報商材って結局どういうものかというと、
なんです。
例えば、あなたが『3ヶ月でTOICE900点取れる勉強法』という教材を買ったとします。
そこには、3ヶ月でどうやってTOICE900点が取れるのか、その方法がまとめられているわけです。
これもいわば、情報商材の一種ですよね。
- TOICE900点を取れる勉強方法=情報コンテンツ
- 教材にして販売する=パッケージ化
- 教材の値段=情報の値段
ということです。
情報コンテンツをパッケージ化して、値段をつけて販売している手法は、そもそもすべて情報商材なんです。
情報商材の共通点:やらなきゃ結果が出ない
先ほど挙げたような、進研ゼミやユーキャン、スピードラーニングなどの情報商材の共通点がわかりますか?
ということです。
実は私も高校生の時に両親が進研ゼミを契約してくれました。
別にやりたいとか思ったわけじゃなく、両親的には塾に行かせるより安いだろ的な考えだったみたいですが(笑)
でもですね、結局進研ゼミの教材が毎月届いても、全然やらないので勉強なんてできるわけないんですよね。
私が通ってたのはそこそこの偏差値の進学校だったので、どんどん勉強は遅れるし、全然授業についていけていませんでした。(特に数学)
同じクラスには、進研ゼミで勉強している人もいましたが、その人は超頭良かったです。確か学年トップ5に入るくらいの頭の良さだったと記憶しています。
という感じに、情報商材って、結局購入した本人次第で全然結果が違うんですよ。
スピードラーニングも、ユーキャンも、同じですよね。
頑張って勉強すれば資格を取ったり、英語がペラペラになったりするかもしれません。
でも、教材(情報商材)に書いてある通りに作業しなければ結果は出ないですよね。
結局は、使う人次第ってことなんです。
情報商材を買ったけど結果が出ない=詐欺?
また、情報商材についてもう1つ考えていただきたいのが、
「情報商材を買ったけど結果が出ない=詐欺」と言えるのか?
という部分です。
確かに情報商材の中には、書いてある通りに実践しても結果が出ないというものはあります。
でも、結果が出ないからと言って詐欺とは限らないんですね。
書いてある通りに実践できていない
詐欺と言い切れない理由の1つは、情報商材に書いてある通りに実践できていない可能性があるからです。
情報商材のデメリットは、コンサルティングではないので、わからないところがあっても基本的には教えてもらえないところです。
結局は、書いてある情報を自分なりに解釈して実践していく必要があるんですね。
なので、情報商材を作った人の意図通りに購入者が実践してくれるかどうかはわかりません。
また、先ほど私が例に挙げたように、サボってしまったり、そもそも購入者がきちんと行動できていないケースも多いです。



自分が実践していないから結果が出ないだけなのに、情報商材を詐欺だと決めつけるのは傲慢です。
自分のレベルに合っていない商材だった
また、情報商材に書いてあることのレベルが自分に合っていないというケースもあります。
例えば、先ほどの『3ヶ月でTOICE900点を取れる方法』という商材を購入したとします。
しかし、あなたが「apple」とか「book」とかの超簡単な英単語すら読み書きできないレベルだったら、おそらく900点取るのは難しいですよね。
商材に書いてあることの1%も理解できないと思います。
情報商材のレベルそのものが自分に合っていない場合も、たとえ結果が伴わなくても詐欺とは言い切れませんよね。
ネットビジネスの情報商材は胡散臭い・怪しいと言われる理由
進研ゼミやユーキャンって、かなり多くの人が使ってると思うんですよ。
実際に、CMもバンバン出していますし、「資格」って検索するとすぐユーキャンが出てきます。
なので、進研ゼミやユーキャンを「怪しい」って思ってる人って、ほとんどいないと思うんですよね。
でも、それがネットビジネスになると、途端に「怪しい」「胡散臭い」って言う人が増えます。
稼ぐ方法も情報の1つ
プログラミングの勉強法や、英語の勉強法になると、なんだか怪しいイメージが無くなりますが、「稼げる方法」を情報商材にするとなぜか怪しいと思われてしまうんですね。
でも、稼ぐ方法だって情報コンテンツの1つですよね。
世の中には稼げる手法がたくさんあります。
こうすれば稼げる!という穴場を見つける人もいるわけです。
そして、その稼げた手法をパッケージ化して販売したものが情報商材というだけであって、何も怪しいことではないんですね。
情報商材で稼いでいたネオヒルズ族が原因
ネットビジネス系の情報商材が怪しいと言われる理由は、おそらく2010年代前半に流行った『ネオヒルズ族』の影響だと思います。
与沢翼さんなんかもネオヒルズ族でしたが、現在は投資家に転身されていますね。
ネオヒルズ族のビジネス手法
ちなみに、ネオヒルズ族がやっていた情報商材の手法をちょっと解説しますね。
ネオヒルズ族が情報商材を売る手口っていうのが、
ってことなんです。
未だにインスタやツイッターで札束を持って「今月はこんなに稼げました♪毎日パーティしてます!」みたいな画像をアップしてる人たちもいますが、あれと同じようなイメージです。
フェラーリを買ったり、六本木ヒルズに住んでパーティしたり、とにかく豪快にお金を使って
ということをアピールするわけです。
そうしたら、(言い方悪いですが)バカな人たちはそれに群がります。



自分もあんな風にフェラーリに乗って女の子とパーリナイできるぜ〜♪
って思っちゃうんですね。
そして、ネオヒルズ族たちが売っている情報商材を購入します。
しかし、その商材の中には「この情報商材をもっとたくさんの人に売ってください」っていう内容が書いてあります。
どういうことかというと、要するにネズミ講と同じような感じで、「情報」だけを媒介にして連鎖的にお金を稼ぐビジネススタイルなんですね。
結局後からその情報商材を購入した末端の人たちは、稼げないまま終わります。
上の方にいる人だけが儲かる仕組みになっているんです。
ネオヒルズ族たちがこのようなビジネス手法で情報商材を販売していたので、情報商材=怪しいと言われるようになってしまったと考えられます。
現在ではこのようなネズミ講方式のビジネス手法は法律で禁止されているので、もし同じことをやったら捕まります。
情報商材詐欺を見分けるポイント4つ



では最後に、そんな情報商材詐欺を見分けるポイントについて解説していきます!
主に注意点する点は以下の4つ↓
- 簡単・手軽にをアピールする
- 「スマホ1台で100万」など明らかな誇張表現
- SNSで勧誘してくる
- 素性がわからない
1.簡単・手軽にをアピールする
情報商材詐欺を見分けるポイントの1つ目は、簡単・手軽にとアピールしているかどうかです。
基本的に、詐欺系の商材は「簡単にできます!」「スマホだけで手軽にできます!」みたいに、簡単に誰でも稼げるということをアピールしています。
そうしないと、誰もその商材を買ってくれないですからね。
まともな情報商材で、特に稼ぐ系の商材の場合は、「簡単」「手軽に」なんて、口が裂けても言えません。
そんな簡単に稼げるなら、世の中の人全員お金持ちになってます。
やたらと手軽さをアピールしてくる商材は注意してください。
2.「スマホ1台で100万」など明らかな誇張表現
2つ目のチェックポイントは、「スマホ1台で100万」など、明らかな誇張表現があるかどうかです。
スマホ1台で100万稼げたら、そりゃあ苦労しないですよね。
今頃日本の消費者金融が全て潰れてると思います。
でも、アイフルとかアコムとか、その辺にいっぱいありますよね。
そんな簡単に稼げるなら、世の中の人全員お金持ちになってます。(2回目)
「隙間時間で50万稼げる」「寝てる間に300万が口座に振り込まれる」みたいなのは全部詐欺だと思ってください。
3.SNSで勧誘してくる
3つ目のチェックポイントは、SNSで勧誘してくるかどうかです。
だいたい詐欺情報商材は、SNSで勧誘してきます。
インスタとかツイッターとかでこんなDMが届いたことないですか?
こういうDMに返信すると、高確率で
みたいな返しが来ます。
そうやって情報弱者を搾取していくわけです。
SNSで金持ちアピールしてる人は見るからに怪しいですが、普通の主婦、女子大生みたいな感じのアカウントからもこういうDMは来るので、絶対返信しないようにしてください。



まともなマーケティングをしている人ならSNSで情報商材売りつけたりしませんからね
4.素性がわからない
4つ目のチェックポイントは、素性がわかるかどうかです。
特にSNSで情報商材を売りつけているような人たちは、だいたい素性や身元がわかりません。
可愛い女性の写真がアップされているけど、「実は中国人の拾い画でした」みたいなことが普通にあります。
- YouTubeなどで顔出しで発信しているか
- 会社名が記載されているか→存在する会社かどうか
- Facebookなどで個人が特定できるか
などは最低限確認した方がいいですね。
まとめ
今回は、情報商材って結局どんなものなのか?についてや、詐欺情報商材の見分け方について解説しました!
情報商材には、まともな情報商材もたくさんあります。
情報商材全てが「怪しい」「詐欺」というわけではありません。



しかし、特にSNSで情報商材を販売していたり、その勧誘をしている人は基本的に詐欺なので、そういった詐欺情報商材には引っかからないようにしてくださいね!